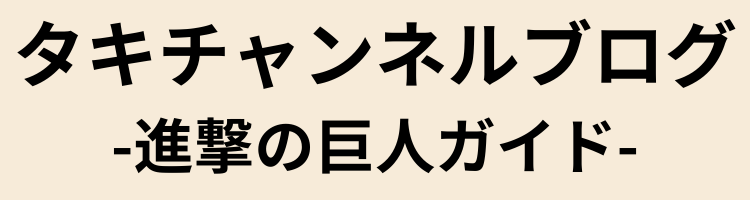この記事の目次
進撃の巨人131話『地鳴らし』のあらすじ
地鳴らし3日目(マーレ国難民キャンプ)
スリの少年ラムジー、ハリルは地鳴らしの犠牲になり、死亡。
始祖ユミルがその光景を見ていた。
エレンの回想(マーレ国潜入)
エレンはスリの少年ラムジーを迷った挙げ句、助ける。
エレンは言葉が通じないラムジーに心情を吐露し「ごめんなさい」と涙を流しながら謝る。
地鳴らし3日目(パラディ島〜オディハ)
地鳴らし中のエレンは、アルミンを道の世界に呼び出すが、そのことをアルミンは覚えていない。
アニはアルミンに感謝をする。アルミンはアニに告白をする。
進撃の巨人131話『地鳴らし』で発生した伏線・謎
残された謎
進撃の巨人131話『地鳴らし』で解決した伏線・謎
進撃の巨人131話『地鳴らし』の表現・対比
進撃の巨人131話『地鳴らし』の考察・解説
進撃の巨人131話『地鳴らし』の考察・解説動画
サブタイトル『地鳴らし』の意味
エレンがマーレ大陸を地鳴らしで踏み潰す。
関連進撃全話のサブタイトルの意味を考察
エレンたちとラムジーの行動の時系列
- ラムジーがサシャの財布を盗む。リヴァイたちが許す。(123話「島の悪魔」)
- ミカサがキヨミ様の別荘でエレンの失踪に気付く。
- 夕暮れの中でエレンが一人で歩く。(今回131話「地鳴らし」)
- ラムジー少年を見かけて助ける。エレン「未来の記憶、先の記憶で見たことがある」
- 「ごめんごめん」と泣きながら謝る。
- エレンをミカサが見つける。(123話「島の悪魔」)
- ラムジーのお爺さん、104期の仲間が来る。
- みんなでラムジーの家で宴会。
エレンの「がっかりした」とは
「壁の外で人類が生きていると知って、俺はがっかりした」とても人間臭いセリフでした。
外の世界は、まだ見ぬ何かがある全人未踏の地だと思っていたが違った。
進撃の巨人の世界は我々の現実世界の延長線上であり、エレンにとってはがっかりする世界。地続きの世界だったということです。このがっかりした気持ちは一部の読者には共通する感覚だったかもしれません。
壁の外は普通に人間が暮らす開拓済みの地で自由に日常を暮らしている人がいるというところ。自分にとっての旅先の非日常は、現地の人にとっての日常であり、まだ見ぬ「何か」がない世界なのです。
さらにがっかりするポイントとして敵がいることです。壁の外の人類が滅んだと聞いていたのにまだ生きていた。それもただの人ではなくて、パラディ島に明確な敵意を持っている存在です。敵が存在しているところで海の向こうにいるのは敵だというところがありました。巨人が壁の外に行くのを邪魔したようにまたしても自由を邪魔する存在がいる。それも我々と同じ人間である。エレンは「望んでいたんだ、全て消し去ってしまいたかった」と語ります。これは純粋な気持ちで思ったことだと分かります。
地鳴らしの決意
エレンが地鳴らし決定するまでの記憶が描かれます。未来の自分が記憶を送っているのです。他の選択肢も検討した結果、これしか道がないと判断しています。
「仲間のため」と「初期衝動」
「そう…すると決まっている、きっとこの先もパラディ島が生き延びる道が見つからなかったんだろう…」エレンは、進むことを決めたのですが、104期生を守りながらヒストリアの犠牲も避け、さらにパラディ島を守る。この他者のため、何とか動こうという気持ちで行動しています。 初期衝動的にがっかりして、全てを消し去りたいという自分の欲求もあったと思います。その二つを交えて地鳴らしを決意しました。ただ、その結果ラムジー少年のような具体的な被害者のこともエレンは当然ながら理解をしているのでまだ迷い、苦しんでいました。ラムジーに対して「ごめん、ごめん」と言っていた気持ちはエレンの本心です。
ヴィリー・タイバーの演説
100話「宣戦布告」でエレンとライナーは会話をしています。ヴィリーの演説を見ると発言がエレンの考えと似ています。「死ぬべきは俺たちエルディア人なんじゃないのか、壁の王が自死の道を選んだように」と、言っていました。ヴィリーも「この世界が直面する危機も全てはエルディア人が存在することによって、生じる危機です」と言っています。理屈は納得できるのですが感情的には納得できないと思います。一方で、このヴィリーも「私は死にたくありません」「それは私がこの世に生まれてきてしまったからです」という。
ライナーとヴィリーの発言からエレンは色々と考えていきます。子供エレンの自由になりたいとか、そのためなら消し去ってしまいたいという気持ちがある。一方で大人エレンは「いや、ダメだ」とか「人を殺すのは良くない」という良心や理性な感情の板挟みに合います。しかし、それを壊したのがライナーの、「俺がそうしたかったから、やってしまったんだ」というところだし、ヴィリーの「死にたくない」という言葉。それらの言葉がエレンの心情とリンクしていきそこでヴィリーの「パラディ島の悪魔と共に戦ってほしい!」と明らかな宣戦布告を受けてもエレンは「進むしかない」と覚悟を決めた切ない顔をしています。
結果的に「建前」「理由」「免罪符」ができたことで進むことを決意します。子供エレンの気持ちに寄り添って、大人エレンは罪悪感を抱きながらもエレンは進むことを決めます。ラムジーを助けた場面と宣戦布告とを重ねて見るとエレンの感情の変化の見え方が変わってくると思います。
被害者から加害者になるエレン
1話「二千年後の君へ」で超大型巨人が出現してからエレンの日常が壊れました。その時に岩が降って来る描写に重ねて今回はラムジー少年たちを岩が襲います。エレンの母親が家の下敷きになり足を潰されてしまったのですが、ラムジー少年たちも岩で足を潰され動けなくなってしまう。巨人の出現によって家族を奪われたエレンが、今度は加害者となって巨人を使って他者の命を奪っていく、というのが切ないところです。
エレンとライナーの共通点
エレンは「俺も同じだったよ、ライナー。半端なクソ野郎だ」と語ります。ラムジーを助けるシーンでライナーのことを思い出していました。これは100話「宣戦布告」で膝をついて謝罪するライナーとエレンの構図や加害者と被害者の関係性が似ています。
このエレンは自由になりたかったし、夢見た世界を手に入れたかった。
一方でライナーは、英雄になりたいという気持ちから動いていた。
自分が将来殺す相手を助ける、という点も共通しています。
後にラムジーを殺してしまうのに何を思い上がってこれから暴力の限りを尽くす俺が正義を気取っていいわけがないだろうと思いながらも、つい助けてしまうエレン。
その姿はライナーがエレンに手を貸した方へと同じです。97話「手から手へ」のライナーの回想シーンで「ただ進み続けるそれしかねえだろう」。挫折しかけたエレンに手を貸して励ますライナーは、後にまたエレンの生活を脅かす選択をしていく。(97話ではその後にライナーが銃を咥えます。)
「俺もお前と同じだったよライナー、半端なクソ野郎だ」ライナーが正体を明かす時の発言をエレン思い出しています。42話「戦士」にて「俺はガキで何一つ知らなかったんだよ、こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに」このライナーのセリフがエレンには、衝撃だったのです。それを踏まえた上で、「いや違う、それ以下だ」と言います。何がそれ以下かというと、「犠牲を生んでしまった人間性」です。この犠牲を意識した上で、助けていることがあるかなと、プラス立ち止まれるのに立ち止まらなかったところもあるでしょう。エレンとライナーの関係を見ていくと、よりエレン理解度が深まると思います。 ライナーにわざわざ会いに行ったのは今後成し遂げるであろうレベリオ襲撃、さらには地鳴らしのおいての覚悟を決めるためだと考えられます。レベリオ襲撃を邪魔されないように足止めするには幽閉手段もあったはずです。
エレンの言葉がブーメラン
エレンの過去のセリフが帰ってきました。46話「開口」でライナーたちに投げかけていた言葉、「一丁前に人らしく悩んだりしてんじゃねえよ。人間じゃねえんだぞ、お前らは。この世界を地獄に変えたのはお前らなんだぞ。分かってんのか、人殺し」
これは、エレンも同じです。43話「鎧の巨人」で「本当にクソ野郎だよ、人類史上こんなに悪いことした奴はいねえよ」と言います。これら全て、エレン自身に返ってきます。人類史上こんなに悪いことした奴はいなかったでしょうし、地鳴らしによりこの世界を地獄に変えたのはエレンです。
エレンとアルミンのすれ違い
二人は壁の外に出たい動機が微妙に違います。73話「はじまりの街」にてエレンは「あの時、お前の話を聞いて、お前の目を見るまでは…」(94話「壁の中の少年」のシーンと繋がっています。)
この場面でアルミンの言葉を聞いて共通の夢を持ちました。アルミンは知的好奇心から海を見たいと思っていました。一方でエレンは、海自体というよりも海があるのにそれを見る自由がないこと、これ自体に憤りを感じているわけです。海そのものに興味があるわけじゃないのです。「炎の水でも、氷の大地でも、なんでもいい。それを見たものは、この世界で一番の自由を手に入れたものだ」という言葉が象徴的です。エレンからすると自由を実感できるものならなんでもいいが、アルミンはそれぞれのものをしっかり見たかったのです。
この二人のすれ違いが明確になったのが72話「奪還作戦の夜」です。このウォール・マリア奪還に成功したら、海が見られるという話をしていました。アルミンが「壁の外にあるのは巨人だけじゃない、炎の水、氷の大地、砂の雪原、それを見に行こう」という話をしますがそれに対してエレンの表情は「ああ、そうだというな」という様子です。エレンは夢を忘れてしまっているのです。それに気づくアルミンの表情も切ないです。一コマ一コマで、察する様子が描かれています。
対比表現
海と空
海を見せようとしたアルミンに対してエレンは喜ばず、アルミンの方まともに見ていませんでした。一方で、アルミンに空を見せたエレン。ただ、アルミンも何してるのだのようなものでお互いに見せたい夢自体がすれ違っているというか、共感できずに共有できない、それらもあるのだと。血と罪。子供のエレンが大人のアルミンを呼んだときに、純粋無垢で血で汚れてない子供のアルミン、エレンと、罪を背負い血で汚れてしまった、大人のアルミンところも、この未知の世界において、明らかに対比的に描かれているなと思います。
本
アルミンが幼少期に祖父の「外の世界」の本を見て夢を得ました。
逆にエレンは夢を失うきっかけとなったのがグリシャの「世界の真相」の本を見てからです。
自由の孤独
この雲の上で「自由だ」と話すエレンには残酷な現実は見えていません。雲や巨人の蒸気ですべて隠されています。子供エレンの主観で世界を見ていますが、この状態は本当に良いものなのか、自由なのか、という点は疑問です。
子供エレンの一貫性
子供のエレンにとっては、壁の存在や巨人が自分の自由を妨げていること、これが許せないと思ったわけです。邪魔なら一匹残らず駆逐する、外の人類だろうと世界そのものを、壊してやる。この残酷なまでの一貫性のもと、求めた自由は邪魔するものが何もない世界であり、「自由だ」と叫ぶ姿だったのです。 不自由が誰か・なにかから邪魔されることだとしたら、自由とは誰もいないこと・何もないこととも考えられます。邪魔するものがない喜びと表裏一体で、虚無感も感じられます。アルミンともそれは理解し合えない描写では、自由が背負う孤独さを感じられます。
ラムジーについて
まず、ラムジーとハリルですがこの二人はキャラクター名鑑では親友という関係です。 120話「刹那」のエレンの記憶の断片が初登場となります。今回もエレンの回想として再び登場するのは、エレンの地鳴らしによる明確な犠牲者の象徴としての存在だからです。 エレンと、ラムジーの会話はエレン達の発言は「縦」、ラムジーは「横」で書かれています。 「家はこっちだよ」と指を指すラムジー少年の言葉はエレンに通じていません。その観点で見るとエレンが「ごめんごめんと」泣きながら喋っているところは一切言葉が通じていないのに謝罪を続けている。ラムジーの「なんで泣いているの?」も、エレンの謝罪もお互いに通じていないことが分かります。
ラムジーの犠牲と貧困
ラムジー達、難民キャンプの生活について見ていきます。彼らは非常に貧しい生活を強いられていました。冬を越せず亡くなる人が何人もいる。おそらく衣食住の保証がなかったのでしょう。そんな中で123話「島の悪魔」にてラムジーがスリを働き捕まる場面にエレン達は居合わせます。ラムジーが日々、盗んでいたお金も人々が一生懸命働いて稼いだものです。当然、ラムジーは罰さられます。大人たちに「海に放り投げる、右手をへし折る、通りにしばらく吊るしておく」など見せしめの為の罰を下れそうになりますが、リヴァイ達に救われました。この表情がポイントですが悪びれる顔をしていない、喜びに涙しているのです。 そして今回、131話で再びスリを行うラムジーが捕まる場面に居合わせます。エレンは地鳴らしによりラムジーが死ぬことを知っているので悩みますが、大人たちから力づくでラムジーを助けます。そして123話「島の悪魔」の宴会の場面に繋がります。冬を越せない生活環境、食器は破損したものや空き缶です。生きるのも精一杯の生活中、ラムジーという一人の子供を助けてくれた恩人のために彼らは精一杯もてなします。そこへ104期生たちがお酒を持ってきてくれるわけですが、恐らく酒を飲むことなど不可能な生活だったでしょう。人々が集まり、夢のような時間を過ごしたのです。 そして時系列はその後のラムジーの様子になりますが、原作は131話冒頭に戻ります。 ここでラムジーがなぜスリを働いていいたかが分かります。「この袋一杯になるまでお金を貯める、そしたらきっとみんなでいい所に住めるようになるから」と言っています。個人や家族の食事のためではなく仲間全員を救う大義のために罪を重ねていたのです。そして注目すべきは右手です。ハリルの「これ以上盗みを続けたら左手も切られちゃうよ」という言葉から分かる通り罰として右手を切り落とされてしまっていたのです。「自分が死んだらこのお金をみんなに渡してくれ…」とさえ言います。なんという自己犠牲…。
エレンとラムジーの共通点
ラムジーにとっての壁は難民キャンプであり、閉じ込められている状況です。エレン同様この暮らしは嫌で「自由になりたい」と思っていてその為の手段としてお金を盗み、貯めています。ハリルの「もうじいちゃんを悲しませちゃダメだよ」それに対し「でも誰かがやらなきゃ」「冬を越せなかった人が毎年何人も死んでいく、もうそんなのイヤだ」と言います。 ラムジーのこの行動について穿った見方をするととエレンと同様に命の選択をしていたことも考えられます。ここまで追い詰められた生活をしているということは、今、まさにお金を必要としている人もいるはず、ということです。よりまとまったお金を貯めてより多くの命を救うことを選択しているわけです。過去に48話「誰か」にてミカサが「私が尊重できる命には限りがある」というように「誰かを選ぶ、ということは誰かを選ばない」ということに繋がります。このテーマは進撃の巨人の中でも何度も語られてきたルールです。 ラムジーはエレンたち同様、世界から虐げられた存在です。手を汚さざるを得ないのは世界の問題である、という点が共通しているのです。ラムジーの「自由になり仲間を救いたい」というその意思はより強い力、自由を求める強い意志を持つエレンに潰されてしまいます。 初期から一貫する残酷な世界、つまり弱肉強食の「勝てなきゃ死ぬ、勝てば生きる」という世界のルールの下、ラムジー少年たちは勝てませんでした。 このお金を握りしめて「死」に向かう…幸せのための自由への片道切符を潰されてしまうような辛さを感じます。
アニとアルミンの恋愛
頭ベルトルト問題
アルミンの恋心ですが、気になるのが、エレンが言ってたこの一言です。112話「無知」にて「お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前だろうが」について考えます。これはアルミンの元々持っているアニのことを好きな気持ちが、ベルトルトの記憶を得ることで増長された形と考えます。
もともと好意があった
例えば、アルミンが以前、女型の巨人に殺されず見逃されたことについて語ります。31話「微笑み」で「あの時僕を殺さなかったから今こんなことになってるじゃないか」と問うとアニは「ここまで追い詰められると思わなかった」と言ったあと「何で…だろうね」と語ります。 他に好意の予感があるのはアニが「あんた弱いくせに根性あるからね」と言うとアルミンが「アニってさ実は優しいよね」と、お互いの人間性を理解し合うような会話があります。お互いに 認め合っていた所はありそうです。 アルミンとアニの恋愛で考える上でミカサとエレンの恋愛を参考に考えます。ミカサは「私にマフラーを話いてくれてありがとうと」とエレンに言っていたのですが、アニの方も、「私に話しかけてくれてありがとう」とアルミンに言っていました。
アルミンに打算的な面もあったのでは?
アニの「いつ目を覚ますかわからない『女型の巨人(バケモノ)』の相手をすることも争いを避けるためでしょ?」の問いかけにアルミンは明確な否定をしません。即座に否定して愛を伝えることもできたでしょうがそれはせずに、思い悩む表情をしている。アニは切ない顔をして答えを待っているのです。そして立ち上がり去ろうとするアニを引き止めます。
「バケモノ」発言
アニの自分のことを「バケモノ」という自認に対して、アルミンは良い人ではなく自分も「バケモノ」であると伝えます。「多くの人を殺して僕もとっくにバケモノだよ」とアニの気持ちに寄り添うような優しい言葉をかけます。同じ苦悩を抱える仲間であり繋がりを感じます。
地鳴らしの具体的描写
「地ならし」とは「地均し」ではなく「地鳴らし」です。 これは 「地面が鳴る = 地面が泣いている」という表現です。
巨人造形の残酷さ
地鳴らし巨人の足の形状は足の底に土踏まずが無い、プレス機のように潰すことができます。残酷…!! 進撃の巨人では「不思議な出来事」の象徴として花が描かれることがありますが、地鳴らし巨人の場面でも花が描かれています。
妊婦が映る
エレンが母親の姿を思い浮かべるシーンがあります。この世に生まれてない子をこの世に生まれてしまったエレンがその生命を奪うエレンの加害者性が強調されます。「その子」は自由になりたい、助かりたい、など思う権利すら無くエレンによって殺されてしまうというのが非情です。 虐殺は許されない行為と再認識させられる場面でもあります。
辛さと恐怖
今回は「名前ある人」が死んでいくことにより「地ならしとはなにか」を直接的に感じる回でした。 「事故で1万人死にました」よりも「●●さんが死にました」のほうがリアリティを持って苦しいです。 見ず知らずの人ではなく、あのラムジーが死ぬというのが辛いです。そのシーンがとても残酷に描かれます。
巨人から逃げる際にラムジーはお金が入った袋を落としてしまう、それを親友のハリルが「お金が!」と言って巨人が迫りくる中、拾いに戻るのです。ハリルは両手に持てるだけお金を握りしめます。ラムジーは残された左手でハリルの手を引いて逃げます。そして降り注ぐ瓦礫がラムジーの足を潰します。一方でハリルは頭部に直撃して恐らく即死です。そんな姿をラムジーは直視する。ハリルの手にはお金が…。そして二人は希望を握りしめたまま、叶わぬ夢とともに踏み潰されて死亡します。
更には、マーレ国民が逃げ惑う場面もあります。どこにも逃げ場がないことの恐怖も伝わってきます。
ジークの祖父母の牢獄

引用:TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編(前編)
ここは完全にアニメオリジナル描写です。ジークの祖父母はジークのマーレ国の裏切りにより投獄されていたようです。さらに地鳴らしを起こしているのは血縁者であるエレンです。 ジーク祖父母以外の牢屋は解錠され、全員逃げ出している中でジークの祖父が「誰か!」と牢屋の中から助けを求めるシーンが追加されます。 受刑者であっても災害時には避難する人権があることが分かります。しかし、ジーク祖父母の牢屋は解錠されなかった。 かつてジークにより名誉マーレ人になった祖父母がジークによってこのような最期を迎える、と考えると非常に残酷な描写です。
進撃の巨人131話『地鳴らし』の感想・ネタバレ
進撃の巨人131話『地鳴らし』の感想動画
関連記事
| 131話『地鳴らし』 | |
| 132話『自由の翼』 | |
| 133話『罪人達』 | |
| 134話『絶望の淵にて』 |
</p